面白い!「日本史の謎は「地形」で解ける」(その1) ― 2014年08月03日
「日本史の謎は「地形」で解ける」
竹村 公太郎 著 PHP文庫 743円
日本史が結構好きです。
この本は購入しました。
著者は土木屋さんで、建設省の役人だった。
江戸をつくった徳川家康は、日本史上最大の国土プランナーだった。
織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちしたのは、
京都へ進軍する際に、地形上、最大の脅威であったから。
また、石山本願寺を攻め落とすのに長い年月を要したのは、
その立地が難攻不落であったから。
石山本願寺の跡地には、秀吉が大阪城をつくった。
源頼朝が流されていたのは、離れ小島ではなく、韮山町であり、
そのため、関東の武士団と密接な関係を築けた。
鎌倉に幕府を構えたのは、当時の平安京(京都)が、あまりにも不衛生だったから。
元寇が失敗したのは、福岡の地形のせい。
歴史上、繁栄した都市は4つの共通点を持っている。
1 安全
2 食糧
3 エネルギー
4 交流軸
食糧とは、米。
明治以前のエネルギーとは、薪、すなわち森林、山である。
福岡には、食料もエネルギーもない。
それでも巨大都市になったのは、海流による交流軸であったから。
などなど、実に面白い。
この項、続く。
竹村 公太郎 著 PHP文庫 743円
日本史が結構好きです。
この本は購入しました。
著者は土木屋さんで、建設省の役人だった。
江戸をつくった徳川家康は、日本史上最大の国土プランナーだった。
織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちしたのは、
京都へ進軍する際に、地形上、最大の脅威であったから。
また、石山本願寺を攻め落とすのに長い年月を要したのは、
その立地が難攻不落であったから。
石山本願寺の跡地には、秀吉が大阪城をつくった。
源頼朝が流されていたのは、離れ小島ではなく、韮山町であり、
そのため、関東の武士団と密接な関係を築けた。
鎌倉に幕府を構えたのは、当時の平安京(京都)が、あまりにも不衛生だったから。
元寇が失敗したのは、福岡の地形のせい。
歴史上、繁栄した都市は4つの共通点を持っている。
1 安全
2 食糧
3 エネルギー
4 交流軸
食糧とは、米。
明治以前のエネルギーとは、薪、すなわち森林、山である。
福岡には、食料もエネルギーもない。
それでも巨大都市になったのは、海流による交流軸であったから。
などなど、実に面白い。
この項、続く。
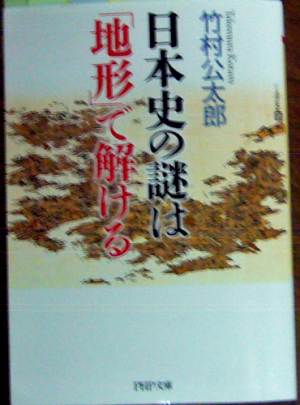
最近のコメント